秋田県秋田市出身。航空会社のCAを10年務め、その後は「接遇講師」としてキャリアを積む。38歳で脳卒中を発症。1年後には、脳の血管腫の手術をする。その後、2024年3月に女の子を出産。現在、育児休暇を取得中で、休暇が終わってからは、新たに「医療関係者のためのセミナー」と「美容とおしゃれに関するアドバイス」をするためのプランを施策中。
病気になりたくてなった人はいない
みんな不安や悩みを抱えている
ちょっとした「声がけ」がどれだけ
患者の安心につながるか、
それを実感している
「モテる人、なんだろうな」。山下明菜さんの第一印象として、真っ先にそう思いました。明るい表情と、上品な言葉づかい。同じ女性の中でも「山下さんのファンは多いはず」と感じさせたのです。山下さんは、エアラインの客室乗務員を10年務め、「接遇講師」に転身。そうしたさなかに脳出血を発症し、失語症になりました。しかし、リハビリを重ねて講師業を続け、1年前には念願の「ママ」に。ていねいな話しぶりと、負けん気の強さが同居している山下さんに、「闘病から人生開花」した経験を聞いてみました。
30代後半で
脳に関わる手術を2度経験。
「やってやる」の負けん気が。
―山下さんの職業は「接遇講師」とうかがいました。「せつぐう」という言葉を初めて聞く人もいるかもしれませんので、簡単に説明をしていただいてもいいでしょうか。
山下:接遇講師を一言で表すと、「相手に対する思いやりをどう表現するか」を伝えていく職業です。「接客」はマナー、敬語、笑顔といったところですが、「接遇」は、他人に対する言動や振る舞いを伝える仕事なんです。
―接遇講師の前は、どんなお仕事をされてきたのでしょう。
山下:社会人になって、航空会社のCA(キャビン・アテンダント=客室乗務員)を10年間、していました。そこで「おもてなし」やマナーを、学びました。CAを10年経験してネクストキャリアを考えたときに、接遇講師を選びました。自分がお客様に「接する」のではなくて、接する人たちを「育てる」方向にシフトチェンジする。CAから接遇講師になる方もけっこう多くて、先輩が同じ会社で働いていたというのも理由です。
―接遇講師として活躍しているさなかに脳卒中を、そして失語症を発症されたのですね。
山下:私のSNSタイトルにあるように、「ある日突然やってきて、それまで当たり前だったことが、いきなりできなくなる」、それを38歳で経験したんです。「人に伝える」仕事をしているなかで、言葉が話しづらいのは致命的でしたし、ここからどうやっていこうか、すごく悩みました。
―「ここでキャリアをあきらめないといけないのか」。そんな気持ちにもなった、と。
山下:私は2021年の8月に、脳出血を発症しました。考えていることが、言葉にできない。疲れているのかなと思ったら、脳出血でした。その時は4カ月入院して、さらに1年後に 脳血管腫の手術をしてまた4か月入院したんです。「ここまでリハビリしてきたけれど、またやり直しなんだ」。途方に暮れる気持ちは、今でも覚えています。
―1度の発症でも「おおごと」だったのに、次は手術。精神的にもショックだったでしょう。
山下:手術のときに、「2週間入院していたら大丈夫」という話を主治医から聞いていたんです。それで安心していたら、後遺症が出てしまって…。それも、ちょっと強めに出たので、「本当に復職できるのかな」「もしかしたら、他の部署に異動になるかもしれない」と、不安との戦いでした。
―その時に「支え」になったものは、何だったのでしょうか。
山下:「半分は絶望。でも、半分は希望」を心の中に持つようにしたんです。「最初の脳卒中の時はリハビリして話せるようになったのだから、同じようにリハビリしていけば、また戻れる」と割り切ったんです。私はすごく負けん気があって、障害や病気を「自分の強みに変えてやる」という気持ちが強かったのです。自分の中での「いいほうのエネルギー」に変えて、「やってやる」みたいな気持ちもあったんですよ。
―リハビリでは「書くこと」を相当、練習していたと聞きました。
山下:入院していて、リハビリの時間は案外、少ないじゃないですか。1日に15分とか、30分くらいしかなかったり…。だから体調が許すときには、ひたすらノートに「あいうえお」を書いていました。私の場合は「五十音」が、ままならなかったのです。知り合いの名前を漢字で書いたり、頭の中で思い出せるものを書いたりとか、かなりやったと思います。
「間を恐れない」ことで
会話に余裕を持たせる。
―話をうかがってみて、失語症を経験したとは思えないほど言葉がスムーズに出てくると、びっくりしたのですが…。
山下:コツというのは私自身わからないんですが、「間(ま)を恐れない」ことは会話の中で意識しています。講師業をしていると、「待つ」ということが結構大事になるんです。相手に考えさせる目的で、問いかけて、あえて間を取る。私自身が失語症になって、どうしても間ができてしまうんですが、「間を恐れない」意識を大事にしています。
―「言葉をつなげないと…」と焦ってしまうのではなくて、あえて「間をとってみる」と。
山下:これは講師をやっているからこそ、わかったことだと思います。職場に復帰した後は、オンラインで接遇の研修をしていました。リモートの操作であったり、そういうサポート業務を同僚に依頼し「私がもし言葉に詰まったら、お願いね」という感じで、必ず安全策を取っていました。
―やっぱり言葉に詰まることもあったんですね。
山下:それはありましたよ。特に「質疑応答」になると、自分では予期していないことを聞かれたりするんです。オンラインで研修をすると、ゆっくり話をして単調になって、受講生が飽きてしまう…というのが実際にあったんですね。自分の中では、「言葉を間違えたくない」という思いがあって、かといって「落ち着いて話をしたい」というのもあって、私としては、ていねいに話しているつもりが、逆に、研修としては「もうちょっとメリハリを出した方がいいよ」と同僚に言われてしまって…。
―失語症になる前だったら「気をつけます」で済むところなのに…。
山下:そうですね。これは大きな葛藤でした。失語症なので、やっぱりできるところまでやりたいんですけど、なかなかうまくいかない。すごく悔しい思いをしました。
―負けん気の旺盛な山下さんだけに悔しかったでしょうし、「プロ」としてのプライドもありますからね。
山下:本当に悔しかったですね。ある程度の日常会話は以前とそんなに変わらないようにはできていたつもりだったので…。プロとしてお金をもらっている以上、やっぱり、しっかりとしたものを提供したい思いがある。だからこそ、悔しかったんです。育児期間で休職中の今も、少しでも改善できるのであればと思って、「早口言葉」の本で練習しています。「毎日、何分やる」というのは私自身、なかなか続かないタイプなので、ちょっとした時に手に取るようにしています。
―先ほども触れましたが、山下さんは育児期間で休職中ということで、でも、今は復帰後のプランを立てていると聞きました。
山下:大きくわけて2つあるんですが、まずは「医療従事者向けのセミナー」を増やしていきたいと思っています。患者として気づいたことが色々あるので、その経験を医療従事者に伝えていったほうが、接遇講師として役に立てるのかな、と。
―入院した病院で、何か感じた部分があった…と。
山下:入院して初日にびっくりしたのは、看護師さんが「ため口」だったことなんです。「今日のご飯どうする?」とか「お風呂、入る?」みたいな感じだったので、そこに違和感を覚えました。CA時代には考えられないことだし、社会の常識として「私より絶対、年下だよね」って…。私が接遇講師という仕事をしているからかもしれないんですけど、すごく気になってしまって。
―わかります。私の経験でいうと、最初は「病院の人がおかしいのでは」と思うんですが、そのうち「自分のほうがおかしいのかな」に変わってくるんです。
山下:必要以上に、堅苦しい敬語である必要はないのですが、せめて「ていねい語」で話してほしいなと思って…。その他にショックだったのは、回復期の病院で担当の看護師さんが、私に対してすごく無関心だったことなんです。たとえば私が、ご飯をまったく手がつけられなかったり、気分が落ち込んだり、体調が優れなくて食べられないときでも、「何かあったんですか?」というふうに、一言あってもよかったんじゃないのかなって。そういうのがない看護師さんだったんですよ。
―そうですか。う~ん…。
山下:すごく忙しそうにされていて、そのフロアの看護師の取りまとめみたいな方でした。抱えている業務が多いのかなって、はたから見ていて思っていたんですけど、ちょっと残念だなぁって思って…。でも、その看護師さんが退院の日に、目に涙をためて「頑張ってください」と言ってくれた。ああ、この人にもこういう気持ちがあったんだな、だったら最初から伝えてほしかったという気持ちになったんです。医療従事者に対しては、私は感謝の気持ちがすごく大きいんです。医療事務向けのセミナーは、そういう方々に対する私なりの恩返しだと思っていますし、医療関係者の人たちの一言で、患者さんがすごく救われると思うんですね。
―2つあるプランの「もう1つ」は何でしょう。
山下:ハンディがある人でも、おしゃれに見えるように、片手で使えるアクセサリーだったり、メイクだったり、それを紹介して、病気を持つ人の気持ちを少しでも楽に、自信を持って生活をしていただくヒントになればと思っているんです。
病気をした自分への劣等感。
おしゃれは「武装」だった
―山下さんも、とてもおしゃれですよね。
山下:おしゃれをすることが、もともと好きだったっていうのもあります。でも私の場合は、失語症とか目に見えない機能障害の病気をしてしまったので、はた目にはわからなくても、病気をした自分に対して、すごく劣等感を感じていたんですよ。もともと華やかな業界にいたことが大きかったかもしれないんですが、周りの人たちと自分を比べてしまったり…。でも、自分の背中を押してくれたものが、おしゃれだった。おしゃれは私にとって「武装」だったんです。
―これも、入院生活がきっかけになったのでしょうか。
山下:私は幸運なことに麻痺がなかったんですが、同じ病室の方は片麻痺だったんです。メイクしたくても「片手でまゆ毛の描き方がわからない」と、嘆いていました。その方に「どうにかしてあげたい」という、そういう思いがベースにあるんです。毎日、ずっとおしゃれでいる必要はないと思いますが、おしゃれをすると、人と会うきっかけになったり、自信を取り戻したりできるのではないか、と。おしゃれが自分のスイッチになることを、私自身の体験から感じているんです。
片麻痺の方でも受けられるオンラインでのメイクレッスンを準備中です。
―先ほどの「医療従事者向けのセミナーをやりたい」という願いも、山下さんは、入院した時の経験に立ち返って、「今のままじゃ、ほうっておけないよな」という気持ちでいるのではないのかな、と。
山下:「ほうっておけない」という気持ちは、確かに言われてみると、私自身、しっくりきます。医療従事者向けのセミナーは、私自身の経験や強みを社会に還元できる方法だと考えていましたが、根底にはそのような思いがあるんだと思いますね。医療機関での接遇は、ホテルや一流店のようなかしこまったものである必要はないのですが、そのかわり、親身になって寄り添う姿勢や態度が大切だと思うんです。病気になりたくてなった人は、いないんですよ。そして、みんな不安や悩みを抱えているんです。「タメ口はNG」などのマナーは基礎として必要ですが、ちょっとした「声がけ」がどれだけ患者の安心につながるか。私自身、それを実感しているんです。
子どもを抱いてあらためて
わかった「医療現場には
頼りになる人がいる」
―今は育児期間ということで、念願のママになったんですよね。
山下:今年の3月に1歳の誕生日を迎えました。女の子です。
―病後の出産ということで、不安もあったと思うのですが。
山下:もちろん、すごく、すごく不安でした。やはり疾患を抱えていますし、出産は頭にもかなり負担をかける。出産自体が体に負担をかけることなので、血管がまた切れてしまうではないかとか、本当に不安だったんです。なので、かかっている主治医がいる大学病院での出産を選びましたし、脳が痛みを感じないように無痛分娩を選ぶなど、やれることはやって臨みました。だけど、やっぱり生まれるまでは非常に不安でしたよ。
―そして1年前に「ママ」になった、と。
山下:もともと私は、不妊治療をしていたんです。そこから脳出血をしたので、いったんお休みをして、そうしたら血管腫も見つかった。すぐに取らなくてもいい血管腫なんですが、この先の人生を考えて、やっぱり出産したい気持ちがあったので、手術に臨んだんです。手術を終えたらもう1度、出産にチャレンジしたかった。もちろん不安もありましたけど、「あきらめきれない」気持ちがあったんです。
―生まれた赤ちゃんを抱きかかえて、真っ先に思ったことは何でしたか。
山下:なんだろうな…。母子ともに健康であることが最優先だったので、生まれてきた子どもと、私の体に「ありがとう」という感じでした。サポートしてくれた医療従事者の方にも、感謝の気持ちで一杯でした。
―山下さんにとって、医療関係者の人は、過去に悲しい事はあったけれども、やっぱり「頼りになる人」なのですね。
山下:そうですね。実は、リハビリ病院を退院する前に、セラピストの方々を集めて「30分だけ」と言って、パワーポイントを使って研修の練習をさせてもらいました。私が「研修をしたいんだけど」と思っても実現するのは無理だったでしょうし、協力をしてくれた医療関係者の方がいてくれたからこそ…だったと思うんですね。作業療法士さん、言語聴覚士さんの方たちが一緒に企画をしてくれて、病院の中にメールを流したり、セミナーにも来てくれた。本当に皆さんに支えられてのことで、自分1人では到底、実現することはできなかったんです。本当に感謝していますし、病院の人のおかげだと、今でも思っているんですよ。
困りごと
脳出血の後遺症で
失語症に
38歳の時に、脳出血になった。簡単な会話が難しく、考えていることが言葉にできない。
2度目の入院で、
症状が悪化
リハビリをして、回復したが、血管腫を除く手術の後に、悪化した。50音もわからず、名前も言いにく、絶望する。
医療従事者の言動に
違和感
年下の職員がため口。患者に対しあまり関心がないようす。接遇講師として気になることがたくさん。
復職できるのだろうか
不安がいっぱい
講師は、話す仕事。説明だけでなく、質問に答える場面も多い。失語症が回復したとしても、講師が務まるのか不安。
工夫
やってやる!
というパワーに変換
もともと負けん気が強い性格。
絶望する気持ちもあったけど、この経験を強みに変えてやる!という気持ちが強くなってきた
頼めることは
頼む
オンライン研修の時の操作は、依頼する。また「ことばに詰まったらお願いします」と安全策を取った。
間を恐れない
失語症のために、テンポよく話せないが、会話でできる「間」をおそれないようにする。研修では相手に考えてもらうために敢えて「間」をとることもある。
自分の強みを
活かす
患者経験から考えた医療従事者向けの接遇研修、片麻痺の人でもできるおしゃれ、これらは、すべて自分の経験から生み出されたもの。これから挑戦したい。

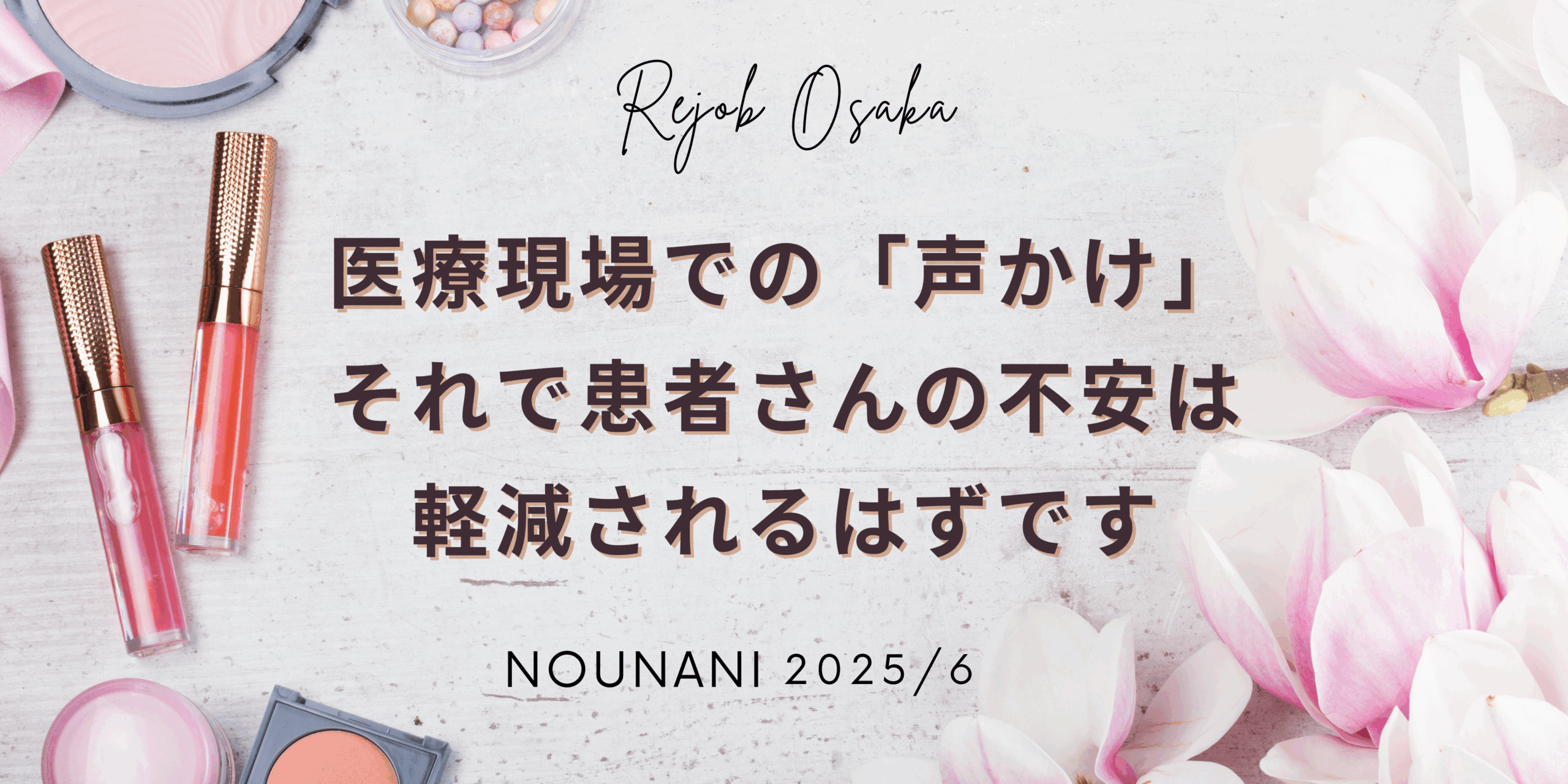








コメント